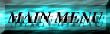連載小説
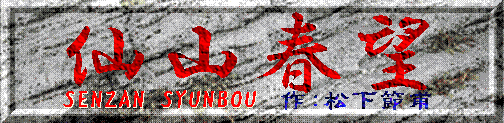
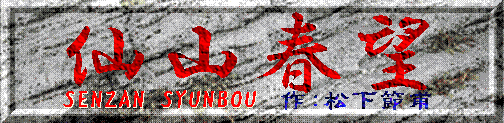
虫の声が、ふととぎれた。
数瞬ののち、再び夜のしじまは破られ、社は虫の声につつまれた。
麗李(れいり)はかれの訪れを察した。香炉に新しい香を入れてから、戸を開ける。
「紅藍(くらん)……」
麗李はかれの名を呼んだ。闇の中にくっきりと、薄翠の光をまとった神仙の姿。
「来てくださったのですね」
麗李は手をさしだした。白磁のようなその手に、小さな螢がとまった。
「今年の、最初の螢です」
紅藍は社の中に入った。麗李はかれを祭壇の前に導いた。
祭壇の上には、見事な錦の婚礼衣装が飾られていた。
紅藍はそれを手にとった。
「いよいよ、明日ですね」
麗李は小さくうなずいた。
「もう、お会いできないのでしょうね。わたくしは神守(かみもり)の家を出るのですから」
「いいえ。あなたはこれからも、神守の巫女です。神守の家に生まれた誇りをあなたが忘れないかぎり、私はいつまでもあなたを守ります」
麗李は微笑んだ。ひざを折り、紅藍の手を頬につける。
「朝まで、ここにいてくださいますか。わたくしが心を残さず旅立てるように」
「あなたが望むなら」
紅藍は麗李に裲襠(うちかけ)を着せかけた。
「あなたは私の巫女なのですから」
社の火が消えた。かわりに、無数の螢が社の中に舞った。
東元の七公のひとつ神守氏(かみもりし)の一女、麗李が入内したのは、元歴六六九年六月のことだった。

紫姫が都に着いたとき、すでにほかの皇子たちや先々帝の皇子たち(白王帝の兄弟たち)は城宮の正殿に集まっていた。白王帝には四人の皇子がいた。
「遅かったではないか」

「手配はすんだか、紫姫」
「送り儀は三十日、御霊納め(埋葬)は来月三日でよろしゅうございますか」
「祭祀は神守氏の役目だ。皆と諮って、よきように、な」
「はい」
紫姫が下がろうとすると、氷見は立ち上がって、異母兄を呼び止めた。
「父上の顔を見てゆかぬか」
「わたくしにその資格はございません」
「父上がそなたを臣に下したこと、うらんでいるのか」
「いいえ。わたくしは神守の家の者。この世の親は仮の親でございます。またこの世の別れが、永遠の別れとも思いませぬ」
「そなたは強い。死すらも自然の流れの中で受け入れてしまえる。私はだめだ」
西の血を受けたことを如実に物語る亜麻色の髪が、二、三度、横にゆれた。氷見は再び牀前に座して、視線を床に落とした。
父王の死に、氷見がこれほど打ちのめされるとは、紫姫には意外だった。
政略結婚で西楼から迎えた楼媛王女を皇后に据えたものの、ほかに恭妃、佳妃、淑妃、側妃の四人の妃と、さらに才人、宝人、尚人、怜人と称される側妾を数多く置いていた父。氷見はそんな父を厭うていた。
「いっそ私など、生まれてこなければよかった……」
自分が背負うことになる責任の大きさに、氷見は押しつぶされそうになっていた。
無理もない。氷見はまだ十四歳である。母もなく、庇護してくれる強力な後ろ楯もなく、ただ皇帝という重圧だけがその細い体にのしかかる。
「氷見どの」
紫姫は昔のように、話しかけた。氷見がまだ皇太子ではなく、紫姫もまだ神守氏の統領ではなかったころのように。
「あなたはひとりではない。私も、羽鳥どのも、翠生どのもいる」
「羽鳥も翠生も、一度ここに来ただけで、城宮にもどってしまったではないか」
「それは、羽鳥どのも翠生どのも草氏の出身ゆえ、禁裏の儀に関われないからです。氷見どのもご存じでしょう」
「しかし、父上が亡くなったのだぞ。それなのに、あまりにも薄情だと思わぬか」
「情はあります。ただ、純粋に悲しんでいる暇がないだけです。羽鳥どのも翠生どのも、それぞれ城宮の警備や楽部の監督に出向いています。そうすることで、亡き帝に対するつとめを果たしているのです。どうか、ご自分の悲しみだけに取り込まれず、まわりに目を向けてください」
「紫姫……すまぬ。しばらくでいい。ここにいてくれ」
紫姫はだまって、八歳下の少年帝に近づいた。一間ほどはなれた場所にすわる。
牀に横たわる父王の顔が、薄い幕の向こうに見えた。
殯宮は静かだった。遠くに、風のうなり。
神守の民があがめる仙山のかなたから、嵐が近づいているのかもしれなかった。

元歴六九三年、十一月。
先帝の喪が明けると、氷見は即位礼をとりおこなった。元朝第二十九代皇帝、氷泉帝(ひょうぜんてい)の誕生である。
氷見は都、按陽(あんよう)に新しい宮を建て、それを泉政宮(せんせいきゅう)と名付けた。
泉政宮に朝廷が移され、新人事が発表されたころ、神守の里にある紫姫の私邸を訪ねてきた者があった。
「晶道士とな。まことか、真乃華(まのか)」
紫姫は側仕えの奥侍女に問い返した。
「はい。お会いなされますか」
「むろんだ」
紫姫は寝椅子から身を起こした。
晶道士(しょうどうし)は東元に帰化した西楼人で、氷見の幼年時代の師である。かつて西楼の楼媛王女が輿入れしたときに、学士の一人として入国した。西の文化を積極的に取り入れようとしていた白王帝は、灰色の髪と青い眼の学士を文官に登用して、道士の地位を与えた。
「斎主どの、ひさかたぶり」
晶道士は椅子から立ち上がり、神守氏の統領に一礼した。
斎主とは、神事をつかさどる最高位の神官のことだ。いまでは神守氏の統領の尊称になっている。
「道士もお変わりなく、なによりでございます。一年、になりますか」
「さよう。いやはや、仙山を歩くのは骨が折れた」
晶道士はこの一年、仙山をめぐって西楼国境と、草氏領南西部の夏火国境を偵察していた。白王帝崩御の影響をさぐるためである。
「して、様子はいかがでございました」
紫姫は晶道士の向かい側にすわった。
「芳しゅうござらぬ。西楼、夏火、どちらもめだたぬように兵を増やしている」
「西楼も夏火も、先帝の送り儀のおりには正規の使者をたててきましたが」
「氷泉帝の度量をさぐるためであろう。帝に国内の七公を抑える力がないと見れば、ゆさぶりをかけてくるはずだ。そのような兆しはないか」
「いまのところは。しかし、地方では小さな暴動がいくつか起こっています」
今年は夏が涼しく、作物の出来が悪かった。もっとも、そのぶん税はいくらか免除している。それでも民が行動を起こすには、何か別の要因があるはずだ。
晶道士はその夜、紫姫の邸に泊まり、翌日、里のはずれに庵を結んでいる峰来老(ほうらいろう)を訪ねた。
峰来老は紫姫の師である。髪は真っ白だが、まだ五十代だろう。「老」というのは、博識の誉れ高い庵の主に対する尊称らしい。
峰来老の庵には庭先から土間や厨にも、犬猫は言うにおよばず、兎や鶏、果ては烏や蛇に至るまで、傷ついた小動物が住み着いていた。紫姫はそれらをひととおりねぎらってから、晶道士を峰来老にひきあわせた。
「西楼も夏火も、隙あらばいつでも国境の兵を動かすであろうな」
晶道士の話を聞いて、白髪の隠者はとつとつと答えた。
「老師もそうお考えか」
「御身が見てきたことが事実なれば、そういうことになるじゃろ。……もう一杯どうかな」
「ちょうだいします」
晶道士は湯呑みを峰来老にさしだした。
神守の里の茶は、囲炉裏の火でじっくりと沸かす。どちらかといえば煎じ薬のようなものだ。
「地方の暴動についても、もう少し詳しく調べる必要がある。都に届いている報告なぞ、微々たるものじゃろ」
「おっしゃるとおりです、老師」
紫姫が答えた。
「首謀者の処遇は地方の知事にまかせていますし、中には治領の乱れを恥として、都に届け出ない者もおります」
「それでは帝が蚊帳の外に置かれてしまうのも、無理はない。……で、晶どの。御身がこの荒屋(あばらや)をお訪ねになったのは、仙山歩きの土産話を聞かせるためだけではなかろう」
晶道士は二杯目の茶を飲みほし、峰来老と紫姫を見た。
「いささか、手前勝手なお願いにまいりました」
「ほう。この世捨て人に、頼み事とな」
「老師と、斎主どのに」
「わたくしに?」
紫姫は晶道士の青い目を見つめた。
「斎主に、帝のそばにいていただきたい」
「これはおかしなことを聞く。帝のおそばには、国内から選りすぐった者たちがお仕えしているはず。紫姫は神守氏の統領じゃ。七公として帝を補佐したてまつることはあっても、侍従のように側仕えをすることなどできようか」
「ごもっともです。私もそのようなことは望んでおりません。ただ、神守氏の統領であるがゆえに、斎主に都に入っていただきたいのです」
「それほどまでに……紫姫に頼まねばならぬほど、泉政宮はあやういのか」
峰来老はため息をついた。
「兵部大臣は薙氏、都の衛士府の大夫(たいふ)は幹氏(かんし)。帝の身辺が安全とは言いがたい」
薙氏は羽鳥の外戚、幹氏は翠生の外戚である。七公といえども、野心を持たぬとだれが断言できようか。過去に謀叛によって断絶した氏もある。
「わたくしなら、まつりごとに関わることはないと信じてのお申し出ですか」
紫姫が訊ねた。晶道士は首を縦に振った。
『神を守る者、現世のまつりごとに関わるべからず』
神守の家のしきたりである。
「わかりました。都へまいりましょう。ただ、城宮の社殿では手狭ですので、いずれかに館を建てねばなりません。それまでお待ちいただけましょうか」
「泉政宮の史書院に一棟あけてもらった。いつでも入れる。新しい館のことは、それからゆっくり手配すればいい」
それを聞いて、紫姫と峰来老は顔を見合わせた。
「用意のいいことじゃ。これは引けぬぞ、紫姫」
峰来老はそう言って、低く笑った。
『南方のめずらしい酒が手に入った。ともに酒杯をかさねたい』
泉政宮史書院の紫姫のもとに、羽鳥からの招待状が届いたのは、十二月に入ってすぐのことだった。紫姫は羽鳥の私邸を訪れた。
「明後日、草原に帰る」
前置きもなく、羽鳥は言った。
草氏領は大半が起伏の少ない草原である。羽鳥は将来の治領を草原と呼んでいた。
「急なことですね」
紫姫は戸口に近い席に腰をおろした。
「叔父上が死んだ」
「草托(そうたく)どのが? では……」
「いよいよ、わしが草氏の統領になるわけだ。そなたと同じように、事実上、臣に下る」
草氏統領、草托には子がなかった。かれは自分の跡継ぎに、妹、明花(めいか)が入内して産んだ羽鳥をと望んでいた。その願いは白王帝に認められ、草托が死亡もしくは隠居したときには、羽鳥が草氏を継ぐことになっていた。
「臣下となることが、ご不満なのですか」
「そうではない。ただ、統領となれば、いままでのように気楽に氏領をはなれることはかなうまい。都になんぞあったときでも、身ひとつで飛んでくるわけにもゆかぬ。神守氏と違って、草原は都から遠い」
草氏領は東元の西端。夏火国との国境地帯である。
羽鳥は自分の酒杯になみなみと酒をついだ。紫姫にはすすめない。
「そなたに頼み事をするのは気がすすまぬが、ほかに人がおらぬ」
「わたくしに、頼みとは」
「翠生のことだ。あれはおそらく、泉政宮で楽部職に就くことになるだろう。まつりごとの場からは遠ざかっているが、皇子の位にあれば、あやうい立場にたたされるやもしれぬ。そのときは、そなたの力で庇うてやってくれ」
またか、と紫姫は思った。晶道士にしろ羽鳥にしろ、自分のことではなく、他人の身を案じ、神守の人間である紫姫に託そうとする。
「なぜ、わたくしなのです。翠生どのの行く末ならば、帝にお頼み申し上げるのが筋というもの。母君、明太妃(めいたいひ)さまは、いまも城宮にお住まいなのですから」
『太妃』とは先帝の妃の敬称である。
「帝、か。ふん。氷見はいま、自分のことで手一杯だ。他人の心配などしておれぬわ」
羽鳥は酒をあおった。からになった酒杯を紫姫の前にさしだし、
「飲め。最後の一杯だ」
と、酒瓶をさかさまにして、滴まで振り入れた。
「めったに手に入らぬ酒だ。他人に飲ませるのは惜しいが、頼み事をする身は弱い」
ほとんどひとりで飲んでおきながら、恩着せがましいことを言う。紫姫は苦笑して辞退した。慣れぬものを飲むと、あとがこわい。
「いえ。わたくしは、けっこうでございます」
羽鳥は紫姫の手をつかんだ。年若い神守の長の顔が、一瞬、気色ばんだ。
「つがれた酒は飲まねばならぬぞ。わしはまだ、そなたの返事を聞いておらぬ。それとも、草氏ごときの頼みはきけぬか」
草氏は百年ほど前に東元に併合された夏火系の部族で、氏として認められてからまだ日が浅い。そのため、七公の中でも低く見られていた。禁裏の儀に関われないのはそのためである。
紫姫は酒杯に口をつけた。強い発酵臭が鼻孔を刺激する。ひと息で飲もうとしたが果たせず、激しくむせた。
「阿呆。そんなにあわてて飲むやつがあるか」
羽鳥は紫姫の体をささえて、背中をさすった。
「大丈夫です」
紫姫は羽鳥の手を払いのけた。
「翠生どのの件、たしかにうけたまわりました。ただ……」
「なんだ」
「翠生どのは、御身さまがお考えになっているほど、お弱くはありません。わたくしの助けなど要らぬかもしれませんよ」
「それならば、それでよい。わしは翠生がかわいい。そなたの都合など、無視できるほどにかわいいのだ」
羽鳥はそう言うと、横を向いた。言ってしまってから照れたらしい。
紫姫は気づかぬふりをして、席を立った。
史書院にもどる途中、楽師寮から楽の音が聞こえてきた。大晦(おおつごもり)に泉政宮で楽部の披露ある。そのための稽古であろう。
紫姫はしばしその場に佇んで、楽の音に耳を傾けた。
あの音は、翠生だ。こよなく愛され、守られている者の出す音だ……。
冬の遠く暗い空に、楽の音は吸い込まれてゆく。その空には、齢(よわい)十六にも満たぬ少年帝、氷見の瞳よりも蒼い星がまたたいていた。

大晦(おおつごもり)。
泉政宮は華やいでいた。年納めの行事もほぼ終わり、あとは新年を待つばかりである。
氷見は年越しの宴を催し、楽部に楽の披露をさせている。昨年の大晦は先帝の服喪期間であったため、例年の行事はほとんど行なわれなかった。翠生たちの奏する楽の音を聞きながら、氷見はよくぞ一年、無事に過ごせたものだと独白した。
紫姫は城宮の社殿で、新年の儀式の準備をしていた。
神守の里では、年明けと同時に山麓にある社を結ぶ道に松明(たいまつ)が掲げられ、人々は新しい年の平安と豊穣を祈って、社から社へねり歩く。城宮の社殿でも、火を焚き、香を投じて山の神をまつる。紫姫は朝まで社殿にこもり、経文を唱えて一年の無事を祈る。これは服喪期間であった去年も、変わらずに行なわれていた。
年明けまで、あと二刻たらずである。
異変が知らされたのは、社殿の火に二度目の香が入れられた直後だった。
泉政宮に派遣されていた神守氏の衛士が、社殿に駆け込んできた。先帝の異母弟、名戸(なこ)皇子が宴席で氷泉帝暗殺をくわだてて、捕らえられたというのだ。
紫姫は濃い紫の長袍に伽羅色の肩布という神守氏統領の礼装のまま、使者の前に現れた。
「帝はご無事か」
「は。されど、翠生皇子がお倒れになり、薬王殿へお移りあそばされた由」
泉政宮の宴において楽の披露を終えた翠生は、その褒美として、名戸皇子が帝に献上した御酒をもらいうけ、それを飲んで倒れた。薬師(くすし)が調べてみると、その酒には致死量の毒が仕込まれていたらしい。
「翠生皇子は亡くなったのか」
「いいえ。お命は、とりとめたようにございます」
「そうか。ご苦労だった。泉政宮にもどってくれ」
衛士を下がらせると、紫姫は淡い藤色の衣に着替えて、参内した。
泉政宮には、兵部、刑部の主だった者たちが集まっていた。兵部大臣である薙氏の統領、多加等(たから)は紫姫を隣席に招いた。
「厄介なことになりましたな、斎主どの」
「名戸皇子はいずこに」
「ほかにも、たくらみに加担した者がおるやもしれません。自害などされぬよう、兵舎の一室に閉じ込めて、黎家(れいけ)の者に見張らせています」
「白家(はくけ)が関係しているとお考えか」
白家は名戸皇子の生母の実家。名戸皇子のくわだてに関与したと疑われても仕方ない立場にある。
「そうでないことを祈るのみですな。白家であれば薬を手に入れることなど、造作もないことですが」
白家は薬方職、黎家は武芸職。いずれも東元の六家と呼ばれる名家だ。封土(氏領)を持つ七公と違い、おのおのの職をもって天子に仕えるのが六家であった。
刑部大臣、侶至更(りょしこう)が入ってきた。紫姫、多加等をはじめ、その場にいた十数人の視線が侶氏の統領に集まった。至更は一同を見回して、重々しく口を開いた。
「名戸皇子は身分相応の死をたまわった」
予想されたこととはいえ、その場にどよめきが起こった。
「して、白家の処遇は」
多加等が訊ねた。
「白石(はくせき)どのは流罪と決まった。多加等どのには、白家の兵をおさえていただきたい。当主が捕縛されるとなると、事の前後を見失い、はむかう者が出るやもしれぬ」
「帝は白家もこのたびの件に加担したとお考えか」
「いや、白家に関しては、あくまでも職務上の過失に対するご処分じゃ」
皇子の処刑というだけでも、世間を騒がすには十分だ。これ以上、事を荒立てず、表に出たものだけを刈りとればよい。帝の意向は各部に伝えられた。
こうして、名戸皇子は夜明けを待たずに処刑された。皇子の身分に対する礼をもって、血を流さぬ方法がとられた。絞首である。
紫姫は氷見の寝殿を訪れた。おそらく一睡もしていないのであろう。青い目の少年帝の顔は、いつにもまして白く、唇の色も悪かった。
「社殿にこもっていたのではないのか、紫姫」
牀(しょう)の上に起き上がって、氷見は神守氏の統領を迎えた。
「帝の大事を聞き、神事を社司にまかせて参内いたしました」
「叔父上があのようなことをするとは……。余には徳がないらしい。翠生がいなければ、いまごろは黄泉路だぞ」
「ともあれ、ご無事でよろしゅうございました」
「そなた、もう翠生には会うたか」
「いいえ。まだお目覚めにならぬと伺いましたので」
「そうか。致死量の毒とあっては、いかに翠生とて、そう簡単には起き上がれぬか」
独り言のような氷見の言葉。紫姫は眉をひそめた。
「翠生どのが、何か」
「そなたも知らなかったのか」
「は?」
「先刻、薬石殿(やくせきでん)の古株どもがあわててやってきてな。なんと言ったと思う。まったく、余をないがしろにしてくれるものだ、ここ(泉政宮)の者たちは」
「薬石殿の者たちが、何を申し上げたのですか」
「翠生に、口役(毒見)の修業をさせていたというのだ。父上が亡くなってから、ずっと」
「それは、どういう……」
「なんでも翠生から言い出した話らしいが、そんな重大なことを、余にひとこともなく決めているのだぞ。まあ、いまになれば、そのおかげで余は永らえたわけだが」
紫姫は氷見の話を反芻した。
「翠生どのは、本当に口役になるおつもりなのでしょうか」
「わからぬ。やさしそうな顔をして、こうと決めたら引かぬところのあるやつだが」
そうかもしれない。翠生も草氏の血をひいている。おのれの目と耳と経験を信じて、草原を渡る部族の血を。
紫姫は翠生の、たおやかな外見に似合わぬ凜とした双眸を思い起こした。混血の進んだ草氏独特の、緑がかった薄い色の瞳。
「そなたはどう思う。こたびは幸い大事に至らなかったが、次もそうとはかぎらない。皇子が口役に就いた前例もないことだし、薬石殿へ通うのをやめるよう、余から翠生に申し渡すか」
「いいえ、帝」
紫姫は小さくかぶりを振った。
草氏領にもどった羽鳥(うちょう)との約束を、自ら破ることになろうとは思ってもみなかった。しかし事ここに至っては、それもやむをえまい。泉政宮に信頼できる口役を置かねばならぬ。
「翠生どののお気持ちが変わらなければ、薬方職に就いていただくのがよろしいと存じます」
年賀の礼が終わるとすぐに、紫姫は翠生の意向を確かめた。答えは「諾」であった。
さっそく各部との調整にとりかかったが、やはり前例のないことに対する反対は強く、結局「口役」ではなく、帝付きの薬師として、宣旨を受けることになった。
薬方職禁廷薬司(やくほうしょくきんていやくし)。
翠生の官名である。
名戸皇子処刑の報は、ひと月たらずのあいだに下々まで広がった。朝廷は民の不安を払拭させるために、都を慶事で飾ろうと画策した。すなわち、氷見の婚礼である。
氷見はまだ後宮を設置していなかった。新しい宮の完成まではと、先送りにしていたのだ。
すでに幾人かの妃候補はあった。七公の縁につらなる者が五人、六家の出身の者が四人。
「みんな入内させればよろしい。後宮がにぎやかになるのは、たいへんけっこうなことです」
と、御前会議で発言したのは、礼部大臣である朱空淵である。この意見をやんわりと退けて、人選は氷見自身が行なうことになった
。
「……は、侶氏(りょし)に降嫁なされました眉良皇女の一の姫でございます。それから黄家(こうけ)の三の姫は、御年十七歳で……」
中書省の官吏が九人の妃候補の出自や年齢などを説明しているあいだ、氷見はじっと目を閉じていた。官吏が説明を終えて自分の席にもどると、氷見は目を開けて、机上の書類の中から二枚を抜き取った。
中書省令である文倉(ぶんそう)が進み出て、その書類を受け取った。すばやく中を確かめる。
「おふたかたでよろしゅうございますか」
「ひとりではだめだというから、二人選んだ」
「して、いずれを皇后におたてあそばしますのか」
「立后はせぬ」
「陛下。それでは後宮のけじめがつきませぬ」
「文倉。皆も聞け。余はまだ若輩だ。これより三年のあいだ、皇后はたてぬ。国内が乱れていることは余も知っている。余の代が、亡き帝の御代のごとく平らかになるか否か、この三年にかかっていると思うてくれ」
もしその間に氷泉朝廷が倒れるようなことがあれば、皇后の位にある者にも累を及ぼすであろう。氷見はそれを憂いているのだ。
氷見が妃として選んだのは、二人ともまだ童姿の似合う少女だった。
商氏出身の蕗邑(ろゆう)姫と、碧家(へきけ)出身の天扇(てんせん)姫。蕗邑は十三歳、天扇は十二歳だった。後宮位は蕗邑が佳妃、天扇が淑妃と決まった。
六九四年、春。
氷見は泉政宮に後宮をもうけ、二人の妃を迎えた。
ひと月後。
翠生はそれまで住んでいた楽師寮から、正室、巳寧(みねい)をともなって薬石殿に居を移した
。
「遅くなりまして、申し訳ございません」
泉政宮に参内した翠生は、氷見に頭を下げた。
「よい。幹の姫のことは余も知っている。変わりはないか」
「はい。おかげをもちまして」
巳寧は幹氏の三女である。現在懐妊しており、大事をとって転居を延ばしていたのだった。
「そなたがまもなく父になるとはな。めでたいことだが、余には少々迷惑だ」
「は?」
「余と一年も違わぬそなたが子を成したとなれば、余にも早く世継ぎをと言う者が出てくるやもしれぬ。空淵あたりは、またぞろ入内をすすめてくるであろうな」
「空淵どのは、二の姫が帝のお目にとまらなかったことが、いまだご不満なのでしょう」
氷見の妃候補の中には、朱家の二女、連理(れんり)の名もあった。
「いや、それはないだろう。空淵の二の姫は、紫姫との縁談が進んでいると聞いたが」
「それは祝着にございます」
「紫姫も二十四。神守氏の統領が、いつまでも独り身でいるわけにもいかぬだろうて。断るにしても、相手が空淵ではなかなか大義だな」
氷見は海千山千の礼部大臣の顔を思い浮かべながら、苦笑した。(つづく)